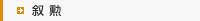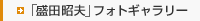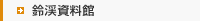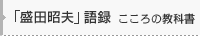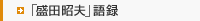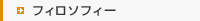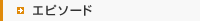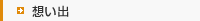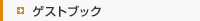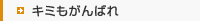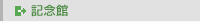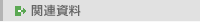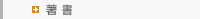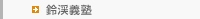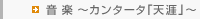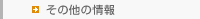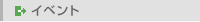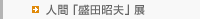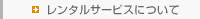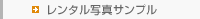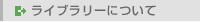8
堂々と、さりげなく
〜 MADE IN JAPAN 全米ツアー
私の書棚の英語版オリジナル“MADE IN JAPAN — Akio Morita and SONY”の隣に、それより一回り小さくてモノクロ表紙の、いわゆる「ゲラ刷り」版があります。1986年10月に初版が発行される前に、数十部だけ試し刷りにつくられたうちの一冊です。
改めて裏カバーを見ると、Tentative Specsとして320pp., 6 1/8 x 9 1/4(頁数とサイズ)などに加えて“Author tour”がある旨の表記。
「ゲラ刷り」は、もともと原稿から版におこす最終手前のサンプル(ちなみにゲラの原語は、galley proofという英語だそうです)とするものですが、もうひとつ、出版元が書店やその筋のメディアに対して「売り込み」をするための先兵として、このゲラ刷りを送りつけるという大事な役割があります。
そして、このAuthor tourというのが、私のアメリカ赴任中、広報の仕事をしていたこともあって、何度となく盛田会長(ここでは、やはり、こう呼ばせていただきます)とご一緒しましたが、そのなかで特に強く思い出に残っているものです。
1986年9月、9West(マンハッタン57丁目のソニーアメリカオフィス)で、ひとりのアメリカ人女性を紹介されました。“MADE IN JAPAN”が全米の書店の店頭に並ぶ頃合いを見計らって、できるだけ全国各地のマスコミに盛田さんの顔と名前を出させよう、というのが、いわゆるプロのpublicistである、彼女(Mさん)のミッション。今でこそ、日本のTVでも、あちこちのモーニングショーやバラエティ番組に立て続けに出演しているな、と思ったら、その人の随筆集が出版されたばかり、ということで、なるほど、と思うようになりましたが、当時、ソニーの広報担当としては、せっかくの盛田さんの、厳粛なる「自叙伝」を、PRのプロの手によって、このように「商品」のように売り込むのは、いささか本意ではありませんでした。それ以上に、盛田さんご本人に対しても、そんなコマーシャルなことをお願いするのは失礼ではないか、と躊躇したのです。
しかし、出版元のE.P. Dutton社は、「これはアメリカではあたり前のこと。本屋の最前列で山積みになるためには、話題にのることが一番。ミスター・モリタが持論をできるだけ多くの人に伝えるのにも、このauthor tourでマスコミの使うのが最も効率がよい」と、かのMさんが今までに誰それの何かという本をベストセラーにした、とその功績を並べ立てています。
さて、盛田さんご本人に、おそるおそる、この「アメリカ式マーケティング手法」を打診すると、なんと即座に「オモシロイじゃないですか」という答えが返ってきました。考えてみれば、Walkman導入の時も、ベータマックス訴訟、ユニタリー・タックス撤廃のときなどなど、率先してマスメディアをうまく使ってきたのは、盛田さんご自身でした。盛田さんこそ、ソニーの「広報マン」として一番活躍された、といって異論のある方はいないでしょう。同時に、好奇心のかたまりのような性格から、このauthor tourなるものを、ご自分もぜひ体験してみたい、と思われたに違いありません。
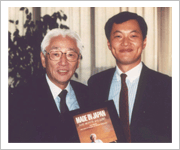 1986年10月
1986年10月"Made in Japan"全米ツアーの盛田さんと杉山さん
かくして、盛田会長、パブリシストのMさん、広報担当サポート(前述のように、ソニー一番の広報マンにその必要はなかったのですが)の私の「三人行脚」は、東はボストンから始まって、西はサンフランシスコ、ロサンジェルスに至る、TV、ラジオ、新聞、ランチョン・スピーチなど、のべ6都市、30回以上のイベントにわたる「MADE IN JAPAN 全米ツアー」となりました。
水戸黄門さまの時代と違って、ファルコンやヘリコプターがあるとはいえ、もともと多忙な盛田さんの時間を、このために確保するのは至難の技でしたが、そこを上手にやりくりしてくれたのが、H. 小野山さんでした。
なにしろ、一カ所で、朝はTVのトークショー、昼はランチョン公演、午後はラジオの生番組を待つ間に地元紙のインタビューという具合で、休まる暇もありません。しかし、周りの心配をよそに、Mさんが組んだ過密スケジュールの「プレッシャー」を、この黄門さまはむしろ楽しんでおられるようで、ツアー中、何カ所か同行された田宮ソニーアメリカ会長も、盛田さんのバイタリティーに、今さらながら感心されていたのを思い出します。
本のパブリシティとはいえ、それぞれのインタビューやスピーチの位置づけは、あくまでも「ソニー会長 盛田昭夫、アメリカの空洞化を憂える」「産業のベースはものづくり」「会社と従業員は運命共同体」などなどがテーマで、正面切って本を売り込むわけではありません。盛田会長は、途中でさりげなく、(この、さりげなく、というのがMさんが盛田さんに特に強調していたことですが)“As I wrote in my book ‘MADE IN JAPAN,’…”とか、“This is what I wanted to say in my new book ‘MADE IN JAPAN’”などと言いながら、相手のインタビュアーや、TVカメラに向かって持論を説くわけです。さすがの盛田さんも、最初のうちはだいぶ面映ゆい感じでしたが、場数を踏んでくるにつれて、生来の「広報マン」センスを発揮、このMADE IN AMERICAのマーケティング手法を、さりげなく、どころか、堂々と折り込んでいかれるようになりました。
もちろん、三大ネットワークTVなどは、本の宣伝とは聞いていても、そこはやはり本来のマスコミの役割を全うすべく、あえてissue raiseしようという意図(とプライド)を示してきます。そのときはトークショーの生番組で、盛田会長と伊フィアット社のU. アニエリ会長(当時)をスタジオに招いて、デトロイトの当時GMの会長だったロジャー・スミス氏とをつないで、日米欧の三産業人対談を仕掛けてきました。
フィアット社はまだしも、日本車の「洪水」のために大きな打撃を受けていたGM社を向こうに回してMADE IN JAPANを論じるのは、しょせん無茶なこと。おまけに、正直いって、言葉のハンディもあるし、と危惧する私たちに対して、またもや、会長は「オモシロイじゃないですか。GMを叩くいいチャンスですよ。」とチャレンジ精神を燃やします。なにか機会があるごとに、前向きに、と立ち向かっていく姿勢には、いつも頭が下がりました。
そして、このディベート・ショーは、「盛田ひとり勝ち」で終わりました。言葉のハンディをなにものともせず、ご自身が強く信じることをとくとくと語る盛田さんの説得力のパワーは、モニター・スクリーン越しのR. スミスGM会長をやり込めてしまったのです。
スタジオから出てこられた会長の誇らしそうなお顔を、今でも懐かしく思い出します。それは、各エピソードの終わりに見せる、黄門さまの笑顔以上のものでした。
こうしてauthor tourを続けるうちに、旅をしているのは、われわれだけではない、と知りました。あるラジオ局に着くと、おりしもライブでインタビューを受けている眼鏡の長身男性がガラス越しに見えます。Mさんが、“That's David Halberstam, the author of ‘The Best and the Brightest.’”と説明します。ハルバースタム氏は、ベトナム戦争の「勇士たち」を描いた同著で一躍有名になったノンフィクション作家で、出版間近の“The Reckoning”という本を引っさげて、同様に諸国を漫遊中ということでした。彼の近著は、ニッサンとフォードをモチーフに、自動車業界の日米逆転を描いたもの(邦訳「覇者の驕り」)で、今から思うと、同じラジオ局なら盛田さんと一緒に対談させたら面白かったろうに、と、例のメジャーTV局と比べると、この地方ラジオ局のおおらかさを感じたものです。
それにしても、この15年ほどの間に、ニッサンはルノーのカルロス・ゴーン氏が乗り込んで再生を図っているし、当時、hollowing outを警告されていたアメリカ産業は、その後、輝かしい(かどうか、もう少し時間をかけて検証する必要がありそうですが)いわゆる「ITリバイバル」を果たすに至り、ハルバースタム氏のいった「覇者」とは、結局のところ、果たしてだれなのか、複雑な思いがよぎります。そして、今、盛田さんがお元気だったら、どんなふうにコメントされるのか、大いに興味がつのるとともに、とても残念でなりません。
ところで、かのハルバースタム氏とは、次の「巡業地」でもすれ違うことになるのですが、ここでも、二人の対談はなされませんでした。
かくして、author tourの成果も手伝ってか、“MADE IN JAPAN”は全米の本屋さんの店頭に山積みとなることとなり、多くのアメリカ人が盛田会長の主張に共感を持ってくれることとなったのはご存知の通り。私は、このツアーを一緒に経験させていただいたことに感謝するとともに、こうした機会を得てMr. SONYとお近づきになれたことを、ソニーアメリカでの(いや、おそらく生涯での)最大の幸運と思っています。
ツアーが終わりに近づいた10月下旬、おりしも私の誕生日であることを知ることになった盛田さんが、ロサンジェルスのレストランで打ち上げを兼ねて、私の「誕生祝いディナー」を催してくださったのも、貴重な思い出です。そして、同席のほかの方々に気兼ねしてか、ホテルに戻ると、部屋に「ご苦労さんでした。Happy Birthday!!」と手書きされ、AKMのイニシャルのついたカードが添えられたプレゼントが、さりげなく置いてありました。まあ、このときの「さりげなく」というのは、会長の、というよりも、今回のツアーでも「助さん」「格さん」以上に、お気をつかっておられたミセス盛田の並々ならぬ「内助の功」のあらわれで、恐縮のきわみだと思ってはいますが。
杉山 勤(2001年 記)
(当時:ソニー株式会社)
※『キミもがんばれ』は、2001年2月、ソニー北米関係有志によって、盛田氏の思い出をまとめた文集(非売品)です。盛田昭夫に関するエピソードやメッセージがあればお知らせください
(匿名・ペンネームご希望の方はその旨も明記してください)
投稿する