![]()
![]()

1964年、今から40年余り前のことです。昭夫と私は3人の子供と共にアメリカ人の生活を知るために、ニューヨークのマンハッタンに1年間住んでおりました。ちょうどそのとき、カリフォルニアに住んでいるアメリカ人の友人がこのようなプレーヤーピアノを持っていました。音の出る珍しいものに興味のある昭夫はすぐに欲しくなり同じようなものを探すように頼んで、手に入れたのがこのピアノです。
ニューヨークからハイウエイを走って1時間半、何の変哲もない家に同じような7、8台の古びたピアノと一緒にそれは置かれていました。この家の主人に案内された私達は、いちばん奥にでんと置かれたグランドピアノの前で立ち止まりました。「これがお望みのピアノです。音をおきかせしましょうか?」家の主は、古ぼけた紙のロールを、手なれた手つきでそのピアノに組み込まれた機械の中にはめ込み、レバーを動かしました。紙いちめんに小さい穴があけられている、ちょうどパンチカードの巻紙のようなこのロールは動きはじめました。
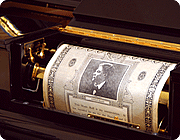
ピアノが鳴りはじめました。リストのハンガリアンラプソディ。
「これは、昔ポーランドの首相でもあり、偉大なピアニストでもあったパデレフスキーが弾いているのです」
「これは ジョージ・ガーシュイン自作自演のラプソディ・イン・ブルーです」
誰も座っていないピアノの鍵盤が、ひとりでに動きます。誰が踏んでいるのでしょうか、強弱のペダルが人もいないのに押されて、美しいハーモニーにイントネーションが加わります。
私は、子どものころ西部劇の映画で見た、たて型のピアノが急に鳴りだした場面を思い出しました。あの時の感じは全く機械的な音でしたのに、このピアノの音には心がありました。この自動ピアノについて、私はそれより1年前、昭夫から聞かされておりましたが、こんなに素晴らしいものとは想像もしていませんでした。
「どうだ。驚いたろう」きょとんとしている私をつかまえて、彼は、もう自分のもののように説明してくれます。この、1921年製のスタインウェイのセミコンサートピアノにデュオアート演奏機が組み込まれた同じ型のものは、当時3台しか作られなかったこと、そして、1台が火災にあって、あともう1台とこれしか残っていないこと。その時、彼は、もはや、この大きなお荷物を日本に持ち帰ることを考えているようでした。
日本がアメリカと戦った第二次大戦後、多くのアメリカ人が日本の骨董品をたくさん持ち帰ったのだから、せめて自分はアメリカの骨董品を日本に持ち帰るのだと昭夫は考えたのですが、私はいったい東京の家に持ち帰って、この大きなグランドピアノをどの部屋に置くつもりなのかしらと考えていました。

後に世界的名ピアニストのワイゼンベルグ氏が、私どもの家に遊びに来られ、ホロビッツの演奏されたものを聞き、「まさしく彼のピアノの演奏だ。若いころの演奏を、今の彼にきかせたい」と、当時そうおっしゃっておられたことを今も覚えております。
指揮者のカラヤン氏は、演奏会の後、家に来られて疲れをプールで癒し、夕食の後、いつもの黒いスポーツシャツに身をつつみ、目を輝かせてこのピアノに見入りました。「素晴らしい」
この大きな、じゃまっけな我が家の居候は、昭夫が亡くなった今でも健在で、毎年調律し、私達を忘れずにこの家を訪れて下さる方々、そして昭夫を知らない若者達が彼の集めた音の玩具を楽しんで下さっております。
2007年5月14日 盛田良子 記




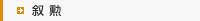

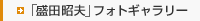


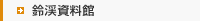
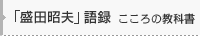
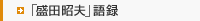
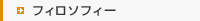

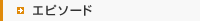
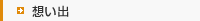
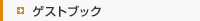
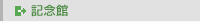
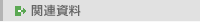
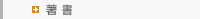

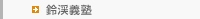
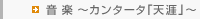
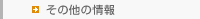
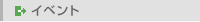
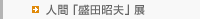


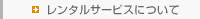
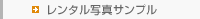

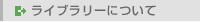


 プレーヤーピアノ
プレーヤーピアノ


